世 界のサンゴ礁保全 日本はサンゴ礁を保全できるの か?
 |
PADI JAPAN(世界最大
の潜水教育組織日本ブランチ) THE UNDERSEA JOURNAL Second Quarter 2003 米国PADI本部・年4回発行。翻訳のため日本は9月発行。 海外の現在のサンゴ礁保全概念を、あまりに生態学的視点の未熟な国内の研究者やサンゴ礁に関心 を持つ人々に伝えます。 これらは、PADI JAPANによる翻訳文を原作者とPADI JAPANの了解を得て転載しています。 ダイブクリエイト佐伯信雄 ・危機にさらされるエコロジー(P3) ドリュ・リチャードソン編集長 ・サンゴ礁の実体(P5〜9) マクギリヴレイ・フリーマン・フィルムズ ・サンゴの白化 次のダイビングまで500年待つ?(P10〜11) アレックス・F・ブライルスキ ・今またオニヒトデの異常発生、サンゴ礁を食い尽くす(P14〜 16) アレックス・F・ブライルスキ ・サンゴ礁は医薬品の宝庫(P17〜 23) アンドリュー・W・ブラックナー ・世界のサンゴ礁の状態に関する詳細レポート(P34) |
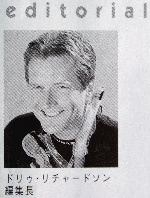 |
ドリゥ・リチャードソン編集長 “私たちは創造に立会い、そしてそれを賛
助する” |
| 人類は何千年もの間、サンゴ礁の
エ
コシステムと共存してき
ました。サンゴ礁は先進国でも発展途上国でも、多くの国家において地域社会の文化や経済成長に重要な役割を果たしています。美しさに惹かれて、世界各地か
ら何百万人もの観光客がサンゴ礁を見にやってきます。サンゴ礁はまた、製薬など様々な製品に利用できる生化学物質としての価値も有しています。生物の多様
性を生み出す壮大な源でもあります。 しかしながら、そういった価値が秘められているのにも関わらず、乱開発、破壊的な漁業、陸地から流れ出る 土壌の堆積、 汚染など人間の様々な活動によって、世界中のサンゴ礁が未だかつてないほどの脅威にさらされています。さらに、地球規模の気候の変化や海水面温度の上昇が 脅威に拍車をかけており、頻繁に過酷なサンゴの白化現象が生じています。様々な環境的ひずみが累積し、世界中のサンゴ礁の未来が脅かされていることを警告 しているのです。 サンゴ礁が重大な危機に瀕しているという認識は広まっているのにも関わらず、研究調査や監視体制が欠如していることもあって、各国のサンゴ礁が どの程度の脅威にさらされているかに関する情報は限られています。そのため、沿岸資源管理に関する有効な意思決定ができないという現状にあります。より広 範な調査を実施しなければなりません。サンゴ礁に悪影響を及ぼす人間活動を理解することが、今後の環境保護や資源計画にとって重要です。十分な調査から得 た確実なデータに基づく意思決定が、サンゴ礁の健全な管理にとって必要不可欠だと言えます。 現在の動向を変えるには、政治的な関心を高め、資金を確保する必要があります。将来にわたってサンゴ礁の活力と生存力を保護するには、この問題 を政府の関係各省庁で優先的に取り上げてもらわなければなりません。これには、管理の行き届いたサンゴ礁の価値について、一般の人々もきちんとした知識や 情報を得て、世論を高めていく必要があります。海洋保護地域を確立し、破壊的な漁業や乱獲を止めさせ、将来にわたって持続可能な観光業を育成し、健全な開 発を推進し、地球規模の気候の変化と温暖化を加速させている排出ガスを規制する政策を導入するには、一般の人たちがそれぞれ関心を持ち、政治的な行動を支 援するという姿勢が必要です。ダイバーは幸いなことに、この目的に向かっての役割と責任を果たす機会に恵まれています。サンゴ礁の環境は、ダイバーである 私たちが心から大切に思っている貴重な資源です。そして私たちは、自ら行動することを選びさえすれば、ひとりひとりがサンゴ礁を守る力を持っているので す。 行動を起こし、自分の意見を表明する方法のひとつが、プロジェクトAWAREの運動に賛同し、その支援者になるというものです。特に、プロジェ クトAWAREのサンゴ礁保護キャンペーンは、サンゴ礁の経済有用性や生態学的価値に関する知識を広め、人間の様々な活動によってサンゴ礁にどの程度の危 機や損傷や破壊が及んでいるかに対する一般の認識を高めることを主眼としています。 プロジェクトAWAREやサンゴ礁保護キャンペーン、またその他の様々な環境保護運動については、www.projectaware.orgを ご覧ください。 最後に、私自身の個人的な理念について少しお話したいと思います。私はこれまでに、友人、親戚、知人を含めて何百万人もの人々と何らかの形で関 わってきたわけですが、その認識に基づいて、私は自分自身を地球というこの惑星に招かれた客人のひとりだと見ています。技術を利用して周囲の環境を操作で きるほどにまで進化した人類という種は、自分たちだけの幸福を追求するという段階をはるかに超えていると思います。人類は自分たちを、自然の中に生きる人 間ではなく、自然と人間は分離したものという形で見ているのではないでしょうか。これは大きな間違いだと思います。自分たちは無敵だという傲慢さが人間の 心の中に徐々に入り込み、人類は生物学的に独立した生き物だという誤った安心感を作り出しているのではないかと思います。核兵器などの大量破壊兵器で自分 たち自身の存在を脅かそうとしている昨今の風潮を考えてみてください。人類が自らの首を絞めているとしか思えません。 人類がどこへ向かっているのか私にはわかりませんが、ひとつだけ確信できるのは、生命の循環は尊く、束の間ではかなく、そして守るべき価値のあるものだ ということです。海、そして特にサンゴ礁の生態系は、私たちに生き生きとした生命力を与えてくれるものであ り、国家を超えた地球規模の預かり物なのです。私はこの地球上で客人として暮らしている間に、海とサンゴ礁の未来を見守る感性を持つ人がで きるだけ増えて欲しいと願っています。私たちが地球上で暮らせる時間は束の間であり、ダイバーはこの責任に対して背を向けてはなりません。 フランスに、私たちひとりひとりに当てはまるLes annees perduという格言があります。これは失われた年月という意味で、無関心や怠慢により無駄に過ごしてしまった時間です。地球全体が危機に直面している重 大事に、無関心で時間を失いたくはありません。地球のサンゴ礁には、もうこれ以上の喪失に耐える余裕はありません。後で考えようでは遅すぎるのです。今す ぐに行動を起こしてください。やらなければならないことはたくさんあります。 |
|
世界のサンゴ礁に関する事実と
情報源
マクギリヴレイ・フリーマン・フィルムズ 世界のサンゴ礁が危機に瀕しています。
乱獲、沿岸開発、地球温暖化による海面上昇などが、傷つきやすく繊細なサンゴを荒廃させ、 サンゴ礁が育んでいる生命のネットワークを破壊しています。 サンゴ礁に関する教育、監視、管理を行っているリーフ・チェック(Reef Check)と国連の地球 規模サンゴ礁モニタリング・ネットワーク(Global Coral Reef Monitoring Network)によると、 過去4年間で世界のサンゴ礁の10%が死滅し、4分の1近くがダメージを受けています。 残っているサンゴ礁の半分以上が重大な危機に瀕しており、現在の傾向がこのまま続けば、サンゴは 今後40年間で完全に消滅してしまう恐れがあると科学者は指摘しています。 幸いな事に、この傾向を食い止め、残っているサンゴ礁を再生させるための新しく持続可能な方法を 考える事に対し、世界的な気運が盛り上がって来ています。 サンゴ礁に関する驚くべき事実
南太平洋 南太平洋には世界で指折りの美しいサンゴ礁があり、健全に生育している場所もあれば、警戒を要する早さで失われている場所もあ ります。何世紀にも渡って、連綿と脈動する島の文化が海に関する様々な神話や伝説を生み出した場所であり、サンゴ礁を救おうという緊急の戦いがすでに本格 的に始まっています。最近行われた調査によると、太平洋のサンゴ礁の約70%が良好な状態に保たれており、残りの30%は中程度または劣悪な状態だと評価 されました。さらに、有毒物質を使って漁をする国からきた遠洋漁船の影響で、人間の住んでいる場所から遠くはなれたサンゴ礁の多くが多大なダメージを受け ています。国連の世界遺産として国内的にも国際的にも保護されているオーストラリアのグレート・バリア・リーフは、漁業、観光、海運などで危機に直面して いるものの、良好な状態に保たれています。メラネシア(フィジー、パプアニューギニア、ニューカレドニア、ソロモン諸島)では、サンゴの生息地に対する人 間の影響を制限するという地元の伝統的な漁法規制のおかげで、多くのサンゴ礁がなんとか持ちこたえています。しかしながら、沿岸の建設工事や土壌の浸食に より、フィジーなどメラネシアの多くの島のサンゴ礁がダメージを受けています。乱獲も問題となっており、特に外国政府が漁業権を持っている場所では深刻な 影響が出ています。タヒチやモーレアがあるポリネシア、アメリカ領サモア、トンガでは、建設工事、農業開発、乱獲などによるダメージに加えて、自然災害で 引き起こされた巨大な波でサンゴ礁が大きな被害を受けました。この地域に点在する小さな島の経済はほぼ完全に漁業に依存しているため、健全なサンゴ礁は人 が生きていくのに必要不可欠であり、サンゴ礁を保護する事に対して積極的な取り組みが促進されています。水温の上昇で脅かされてはいるものの、グレート・ バリア・リーフは様々な海の生き物の宝庫であり、年間10億米ドル以上もの観光収入をもたらしています。ここには、400種以上の造礁サンゴが生息してい ると見積もられています。 アメリカ大陸 米国では、サンゴ礁がフロリダ州の南端に長いカーブを描いて“尻尾”の形に点在する島々を形成しており、その多くが370キロメートルに渡ってサンゴ礁を 保護しているフロリダ・キーズ海洋保護区の一部になっています。保護に対する取り組みは行われているものの、フロリダ州のサンゴ礁もじりじりと間違いな く衰退が進んでいると一部の学者は懸念しています。海水温の上昇がサンゴの白化に拍車をかけている一方、エバーグレーズ国立公園、フロリダ湾、フ ロリダ・キーズにおける観光客の増加と人口増が悪影響をもたらしていることも否定出来ません。ポリネシアに属するハワイ州では、サンゴ礁が観光の目玉のひ とつになっています(注:地理的に見ると、ハワイは北回帰線と赤道の北に位置しているため南太平洋には属しませんが、ハワイ周辺のサンゴ礁の動物相は南太 平洋の動物相と 生物学的に関連しています)。米国に属するサンゴ礁の80%以上がハワイにあり、最新で最大のサンゴ礁公園である北部ハワイ諸島国立海洋保護区にあるサン ゴ礁は、米国の全サンゴ礁の68%を占める規模です。その他、テキサス州とルイジアナ州境の南にあるフラワー・ガーデン・バンクス、プエルトリコ沿岸沖、 アメリカ領ヴージン諸島、そしてグァムにサンゴ礁があります。サンゴ礁からの漁業収益は、合計して年間75000万米ドルになります。またアメリカ大陸に は、バハマ・バンクス群島沖に大部分が未開発の大規模なサンゴ礁があり、さらに世界で2番目に大きなバリア・リーフであるメソアメリカン・バリア・リーフ は、メキシコ、ベリーズ、ホンジュラスの沿岸に沿って約600キロに渡って伸びる広大な未踏のサンゴ礁で、驚くほど健全であり、原始の状態が保たれていま す。ジャマイカでは、ネグリル周辺のサンゴ礁が観光スポットになっていますが、人気を集めるサンゴ礁にどのようなことが起こりえるかを例示しています。ネ グリルのサンゴ礁はかってカリブ海で最も人気のあるダイビング・スポットのひとつでしたが、乱獲され、ウニがいなくなってしまうという被害を受けました。 ここのサンゴ礁では、生長の早い藻類が繁茂しすぎるのを魚とウニが食い止めるという役割を果たしていました。1980年代に入ると、魚とウニが減ったこと で藻類がとめどなく蔓延するようになり、サンゴで覆われている海底面積が以前の78〜80%からたったの5%まで減少してしまったのです。現在、学者と地 元住民が協力して、乱獲を規制することによって被害を食い止める取り組みが行われており、ウニが戻るのを待っています。ジャマイカと同様に、他のカリブ諸 国や中南米の沿岸諸国でも急激な開発が被害を及ぼしていますが、壊れやすいサンゴ礁を守ろうという国や地域による新たな対策が動き始めています。 アジア 南太平洋と同じく、アジアにも世界で最も有名な島々、砂浜、生命あふれる鮮やかなラグーンがあります。しかしながら、この地域のサンゴ礁の多くが世界で最 も深刻な危機に瀕しています。アジアのサンゴ礁のほとんどが、今後数十年間で激しく衰退するだろうと予想されています。現在、アジアのサンゴ礁には100 種類以上の海鳥が生息し、20種類もの海中植物を見ることができます。しかし、アジアの人口は今後25年間で倍増すると見込まれており、サンゴ礁のさらな る乱開発も進むものと思われます。3万以上の島々からなるインドネシアの沿岸には、多数の壮大なサンゴ礁が広がっています。人口が集中している地域から遠 くはなれた場所にあるサンゴ礁は生き物に満ちあふれていますが、ジャワ島やスマトラ島に近い場所では、人間が引き起こした汚染や沈殿により、サンゴ礁が著 しく衰退しています。マレーシアのサンゴ礁の多くも危機に瀕していると見られており、ベトナムでは、水産養殖場の建設と沿岸の干拓事業により、1945年 と比較してサンゴ礁のマングローブが45%以上も減少してしまいました。フィリッピンでは、シアン化物と爆薬を使った漁業により、沖合のサンゴ礁が著しく 荒廃してしまっています。最近では、フィリッピンのサンゴ礁の生産力は3分の1近く 減退し、約30%が死滅したと宣言されています。中国、日本、シンガポールでも、沿岸開発がサンゴ礁に被害を及ぼしています。しかし、希望の兆しもありま す。タイの美しいアンダマン海では、健康なサンゴ礁が勢いよく生育しています。 アフリカ、インド洋、中東 多くの東アフリカ諸国が、広大で生物学的な多様さを誇るインド洋に接しています。ソマリア、ケニア、タンザニア、モザンビークの沿岸やザンジバル島にサン ゴ礁があります。マダガスカル、モーリシャス、リユニオン、コモロなどの島の周囲にもサンゴ礁が広がっています。その約80%が良好な状態ですが、急速に 増えている人口に伴う脅威から免れることは出来ません。ダイナマイトや有害物質を使用した違法漁業が普及し、砂の採掘も広範囲に行われています(モーリ シャスでは、毎年約45万3600トンのサンゴの砂が掘削されています)。アフリカのサンゴ礁に関しては科学的な調査がほとんど実施されていないため、死 滅したり破壊されたりした場合には、人類を苦しめている様々な病気の治療方法なども含めて、計り知れない尊い知識がサンゴ礁とともに解明されることなく失 われてしまうことになります。明るい兆しとして、現在、ケニアに4つのサンゴ礁海洋公園と5つの海洋保護区が設立され、ケニア野生動物公社はサンゴ礁を有 害開発から守る管理計画を導入しています。インドとスリランカの沿岸地域にも人口が密集し、生計をサンゴ礁に依存している暮らしをしています。実際、スリ ランカの人口が必要とする食料の65%が、サンゴ礁の海洋生物によって満たされています。しかしながら、この地域のサンゴ礁も、乱獲、採掘、観光、産業汚 染などによって深刻な危機にさらされています。またこの地域では、サンゴ礁に生息する熱帯魚を捕獲して水族館や一般家庭用に売る商売が盛んに行われてお り、スリランカとモルディブに固有の種が減少するという問題が起きています。これに対し、サンゴ礁の重要性と保護の必要性を地元住民に教える公的教育プロ グラムを開発するという取り組みが現在行われています。中東の紅海には壮大なサンゴ礁が発達しており、リーフチェックが実施した調査では、世界で最も健康 なサンゴ礁と見なされています。しかしながら、その一部もやはり危機に瀕しており、主として石油産業と観光リゾート開発が原因です。イエメン、オマーン、 アラビヤ湾では、石油汚染とずさんな沿岸開発により、サンゴ礁が激しいダメージを受けています。しかし、エジプト、イスラエル、バーレーン、ジブチ、イラ ン、オマーン、サウジアラビヤ、ヨルダン、スーダンにはサンゴ礁保護区があります。 リーフレスキュー 私たちに出来ることは何か:
プロジェクトAWAREのサンゴ礁保護キャンペーンは、サンゴ礁の生態系を保護することの深刻な必要性について一般の人々を教育する啓蒙活動であり、生態 系にダメージを及ぼしている様々な問題に対する日常的な対策に関して人々が行動を起こし、積極的に参加するのに必要な情報を提供しています。サンゴ礁につ いて学び、どうすれば保護できるかについての情報は、www.projectaware.orgを ご覧ください。その他、サンゴ礁の保護に関わっている団体を下記に紹介します。各サイトでサンゴ礁に関する最新情報やデータを見ることができます。 Reef Check www.reefcheck.org Rescue the Reef www.rescuethereef.org The Coral Reef Alliance www.coral.org International Coral Reef Network(ICRAN) www.icran.org Ocean Futures Society www.oceanfutures.org Reef Relief www.reefrelief.org マクギリヴレイ・フリーマン・フィルムズ 世界のサンゴ礁について知りたい方には、マクギリヴレイ・フリーマン・フィルムズの新作IMAX映画「コーラル・リーフ・アドベンチャー」をお勧めしま す。最寄りの上映館に着いてはwww.coralfilm.comを ご覧ください。 |
| 今
またオニヒトデの異常発生、サンゴ礁を食い尽くす アレックス・F・ブライルスキ Ph.D プロジェクトAWARE財団、海洋保護スペシャリスト 少なくともここ40年間、多分それ以前からインド・太平洋のサン
ゴ礁は常に難問に直面してきました。その犯人はいつでもサンゴ礁の隠者、オニヒトデ(英名:clown-thorh-starfish(COTS)、学
名:acanthaster-planci)でした。
今回の爆発的な増加は異常発生とも言われます が、この貪欲なサンゴイーターの大発生は、多くの地域、特にオーストラリアのグレート・バリア・リーフで多くの被害をもたらしています。この無脊椎動物に よるサンゴ食害の最も異常な傾向は、この大発生が一定の周期で起きていることでしょう。最近では、2001年にケアンズの近くのサンゴ礁で起きたときに は、オーストラリアの観光機関はその駆除のために230万オーストラリア・ドルの費用を要しています。しかしながらオニヒトデの異常繁殖は、関係各国やオ ニヒトデを研究している科学者の間では、以前からある問題で、近年ますます大きくなって来たものです。事実、これからお話しするこの不気味で今も未解決の オニヒトデ怪談は、『What Is Natural? Coral Reef Crisis(科学史研究家のJan Sapp著1999年)』によるものです。オニヒトデ(COTS)については今も多くの不明点が残ったままですが、研究によってオニヒトデの生物学的な知 識、異常発生現象の特性、被害にあったサンゴ礁の再生のパターンなどについての理解が深まってきています。 COTS101 COTS(オニヒトデ)の実物はもちろんのこと、写真ですら見たことのない人には、COTSのその異様な姿は、ホラー映画から飛び出してきたとしか思え ないかもしれません。 オニヒトデは大きく(少なくともヒトデとしては)直径81センチ以上にも育つ場合もあります。よく砂浜で見かける普通の5本の腕のヒ トデとは違い、COTSは21本の腕をもっています。オニヒトデは夜行性で、この21本の腕は長くて鋭く、毒をもったトゲでびっしりと覆われています。 COTSの繁殖期は12〜4月、オーストラリアの夏から初秋にかけての季節です。水温が28℃前後になったときに、他の水中生物と同じように、オニヒト デ は精子と卵子を水中に放出します。オニヒトデのメス1匹が、1産卵期に生み出す卵子は2億5000万個にも達します。まずこれが爆発的な異常繁殖の可能性 につながります。 受精卵は幼生となって2〜4週間を潮流の中で過ごしますが、中には魚の餌になるものもいます。この時期を幸運に生き延びた幼生は、1〜2 ミリほどの子供になり、サンゴ礁に定着をして生活を始めます。この間、岩陰やサンゴの陰で過ごすため、他生物の目に触れることはまずありません。この幼年 期、オニヒトデは藻類を食べています。そして1年を過ぎると生きたサンゴを餌とするようになります。2年経つとCOTSは直径25センチほどにまで成長し ます。 サンゴ礁での通常の繁殖密度は1ヘクタール(100x100メートル)当たり12匹程度です。このような繁殖密度では、夜行性で昼間はサンゴの陰に 隠れていて、ほとんど他の生物の目に触れることはないのです。そのさほど高くない通常の繁殖密度からして、大発生が起きるまでは、COTSがサンゴにどの 程度の被害を与えているかはっきりしていません。そのはっきりしない理由はオニヒトデが選んで食べるサンゴに好みがあるからだといわれています。 COTS はテーブル・サンゴと枝サンゴを好んで食べます。だからといって、そのサンゴの郡体すべてを食い尽くすことはしないのです。オニヒトデによるサンゴの食害 も、ある一定レベルであれば、サンゴ礁には復活の可能性があるということです。事実、野火が新しい草木を育てるように、ある一定のサンゴ食害は、サンゴ礁 のリサイクルや生物相の多様性を保つ働きをしてくれます。ところがサンゴを食べる口がそれ以上増えると問題が起きます。個体数が増えるとエサを競って食べ るようになり、さらに食べるエサの好みがなくなって、どんなサンゴも食べるようになります。しかも、夜でも昼でもサンゴを食べるようになります。 いっ たん 異常繁殖すると、繁殖密度も1平方メートル当たり数匹と異常な数になります。このような個体数の異常な増加は珍しいことではなく、一度この異常繁殖が起き ると、数日のうちに生きたサンゴ礁のほとんどを食い尽くしてしまいます。 グレート・バリア・リーフでの調査結果によると、サンゴ礁を覆っているサンゴの普 段のレベルの25〜40あるいは41%ぐらいまで、オニヒトデはサンゴを消滅させたことがわかっています。このレベルまでサンゴ礁が破壊されると、回復す るには10年、あるいはそれ以上かかると考えられます。この説明で、観光関係者やサンゴ礁の管理者がCOTSにより大きな脅威を感じていることを疑う人は いないでしょう。 異常発生の根拠 グレート・バリア・リーフでのオニヒトデの大発生は、 過去3000〜7000年の間、毎年起きていたという見方もあります。この見方は、大昔のサンゴく ず(泥)の中に、COTSの骨格の一部である、針状骨が見られることが根拠になっています。しかしこの見解に対して、サンゴのくず(泥)にはいろいろの年 代のものが混じっていて、正確な年代を特定することが難しく、このような証拠で結論にはならないという異論を唱える研究者もいます。現代におけるCOTS の大発生の記録は、1962年のケアンズの沖にあるグリーン・アイランドでの大発生です。しかしながら、それ以前にも大発生はごく当たり前に起きていた と、多くの人が考えています。この人たちは、スクーバ・ダイビングが広まったために、この40年ほどの間、大発生がたまたま目につくようになったと考えて います。研究から、この異常繁殖現象のメカニズムを説明する理論は互いに関連するのでしょうが、3つに分かれています。ただし、どの理論も立証された訳で もなければ、否定された訳でもありません。 それぞれの理論は以下の通りです。 1) COTS(オニヒトデ)の個体数の変動は自然のことである。 2) COTSの天敵(捕食動物)を獲るとCOTSが増える。 3) 人口の増加に伴って栄養物が海に排出され、COTSの幼生の 生き延びるチャンスが大幅に増した。では、それぞれの理論を見ていくことにしましょう。 自然の成り行き説 ほかの無脊椎生物と違ってCOTSは生きている間に、 10億近くの卵を産むことが出来ます。このことはある環境条件の変化が、その生存率に大きな影響を 与えることを意味しています。例えば、1億の幼生から1個体が生き延びる場合から1000万個に1個体が生き延びるように生存率が変化すると、1世代の個 体数でも10倍に増えます。環境の変化要因には、水温、塩分濃度、エサの獲りやすさ、そしてそのいずれもが幼生の生存率を大幅に高めてしまいます。 最近で はこのCOTSの異常発生がエルニーニョ現象と何らかの関連性があるのではないかといわれています。北アメリカでは、このエルニーニョが熱帯太平洋周辺で の大きな気候変動を引き起こしています。ドミノ倒しのように、COTSの成体個体数の増加が起きるだけでも、膨大な数の産卵が起きることになり、次世代の 幼生の生存率を大幅に高めることになります。科学のあらゆる分野で数学的モデルが使用されているように、COTSの個体数をコントロールするための幼生の 被捕食率が数学的に試算されています。ところが、最近の研究ではCOTSの幼生や未成体の被捕食率は、推定した率よりも低いことがわかってきました。そこ でさらなる研究が続けられています。 人為的な要因 研究者の中には、世界的に見て、雨期とCOTSの異常 発生との間には何らかの関係があると考えている人もいます。この考え方は降雨が大量の泥とともに栄 養物を海に流入させることになり、オニヒトデの幼生の食料減である微小な藻類を増加させます。その結果、幼生の生存率が普通の条件下に比べて高率になりま す。さらに他の研究者は、大量の真水の流入による塩分の低下が COTSの幼生の生存率を高めるという説を提唱しています。この説は、ヨーロッパからの移住が始まって以来の社会活動の増大、そして人口の増加によって、 栄養分が著しく増大していることを考えると、少なくともグレート・バリア・リーフでは、ある程度の信憑性があります。もうひとつの説は、大発生はもともと 自然なことなのですが、栄養分の蓄積が大発生の頻度と集中度に影響を与えるというものです。 捕食動物(天敵)がいない と… もともとタフであること、しかも有毒の皮膚と長いトゲをもつ成体 のCOTSにはほとんど捕食者(天敵)がいません。いくつかの説では、オニヒトデの捕食 者が個体数の爆発的増加をコントロールするカギを担っているとしています。この説はよく知られたオニヒトデの捕食動物(天敵)であるジャイアント・トリト ン(ホラ貝の1種)に、人々の目を集めさせることになりました。 この説は、1969年に少なくともオーストラリアで保護が始まるまでは、シェルのコレク ターによって大量に獲られていたので(異常繁殖が起きるようになっても、保護指定がされていない地域では大量に捕獲されています)、理論的に説得力があり ます。ところが最近の研究では、このホラ貝は1週間に1匹のCOTSしか食べれないこと、異常発生をコントロールするには、はるかにその数が足りないこと が結論ずけられています。 異常発生をコントロールする COTSの異常発生が最初に記録されたこともあって、 COTSのコントロールについての研究の多くは、グレート・バリア・リーフとその管理機関、グレー ト・バリア・リーフ海洋公園局(GBRMPA)によるものです。これらの研究からCOTSの異常発生そのものを防ぐことはできないものの、多くの人為的な 努力を重ねれば、地域的には異常発生による被害からサンゴを守ることができます。 オーストラリアでは、硫酸ソーダ溶液あるいはその他の化学薬品を、トレー ニングを受けたダイバーがヒトデに注射しています。オニヒトデは数日のうちに死にますが、これだけではすぐに新たに管理地域に入ってくる個体を止めること はできません。このCOTSの素早い移動性は、個体数の日常的な管理を要求します。その結果、COTSの個体数の管理は、経費面でも、労力の面でも、ひど く手間のかかる事業になります。 例えば、ケアンズ沖の硫酸ソーダの注射などによるオニヒトデの駆除は、1日200〜500匹を駆除するだけでも、観光関係 者は年間30万オーストラリア・ドルを費やしています。しかもこのやり方は、あるごく限られた地域、例えば商業的あるいは観光価値が非常に高いといった地 域に限って実用的です(水中で殺すだけでは、オニヒトデの個体数管理になりません。それぞれの身体の部分が再生して、より多くの個体になります)。 観光に 与える影響はともかく、この問題をさらに面倒なものにしているのは、このCOTSもまたインド洋/太平洋の一部だということです。もしその異常発生が自然 の営みの一環であるとすると、母なる自然を無視して、COTSの大発生を管理しようとする試みは、長期的に見て生態系にどんな結果をもたらすのでしょう か。科学のあらゆる分野と同様に、このような問題に対して、まだ私たちは答えをもっていないのです。この針坊主のような海のお化けの謎も、COTSの生息 する環境についての理解が進んで初めて明らかになるでしょう。 研究者たち、特にグレート・バリア・リーフ周辺の研究者はその答えを求めて研究を続けていま す。陸からの真水の流入と大発生の関連性、より利益効率のよい管理方法、長期的管理のサンゴ礁の生態系への影響などを含めて、様々な研究が続られていま す。現在私たちが知り得たこともたくさんあります。さらにCOTSについて勉強したい人は、Australian Institute of Marine Science(オーストラリア海洋科学研究所)のホームページ、http://www.aims.gov.au/web/guest/search?q=Cod にアクセスしてみてください。 |
|
地球規模サンゴ礁モニタリング・ネットワーク(Global Coral Reef Monitoring Network、GCRMN)とオーストラリ
ア海洋科学研究所(Australian
Institute of Marine Science、AIMS)は先頃、世界17地域100カ国以上のサンゴ礁の状態に関する詳細情報を記
載したレポートを発表しました。 朗報 問題点 次は? |
Top|計画&報告|海浜清掃|メンバー|オニヒトデ|世界のサンゴ礁保 全|会則|サイトマップ